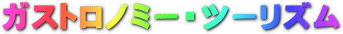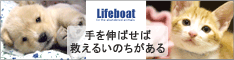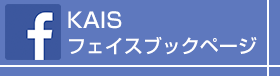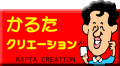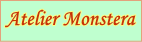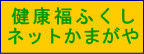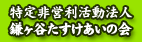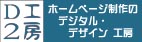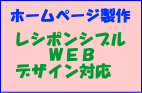-
-

食欲をそそる日本食料理
-
「片雲の風にさそわれて、漂泊の思ひやまず・・・」と旅立ったのは松尾芭蕉。 みなさんの「旅」の目的は何でしょうか?名所・旧跡を訪ねる。名湯・秘湯で温泉三昧。あの映画やドラマのロケ地を訪ねる。美味しいものを食べる。など、さまざまな「旅」の目的があると思いますが、「食べる」という「旅」を考えてみようと思います。さまざまな名産地がありますがその美味しさは格別のものがあります。
島根県の郷土料理『宍道湖のしじみ汁』。宍道湖は汽水湖。そこで育つ「大和シジミ」は柔らかくて味が濃い、そしてなにより一粒ずつが大きい。それは、資源保護のため小さなシジミは獲らないという「決め事」を漁師さんたちが守って、品質の維持に努めているからなのです。
高知の『カツオの塩たたき』。もともと高知はカツオ漁の盛んなところ。カツオの美味しさを追求したのが、藁焼きで風味と旨味をとじ込める調理法。厚めに切ったカツオを藁の火で焼き、地元で作られた天日塩をふって食べる。その味はおもわず「おぉ、これは・・・」と、うなってしまう美味しさです。
美味しいものを食べ、地域ならではの料理を発見すること。そんな目的で、旅をする「ガストロノミー」と言われる人たちが増えているようです。「ガストロノミー」は「美食家」と訳されますが、食材の来歴やその生産状況や調理法など、あらゆることに関心をよせて料理を味わっている人です。例えば、人気コミック『美味しんぼ』の登場人物 山岡士郎や美食倶楽部の人たちをイメージするといいかもしれません。
そうした人たちの旅がガストロノミー・ツーリズムです。国連世界観光機関は次のように定義しています。『観光客の体験・活動が、食や食材に関連付いていることを特徴とする。本格的、伝統的又は革新的な料理体験と併せて、ガストロノミー・ツーリズムには地域の産地訪問、食に関するフェスティバルへの参加、料理教室への参加など、他の関連活動を含む場合もある。』というもので幅広い概念ですね。
2024年10月22日に放送されたNHK「クローズアップ現代『美食』が地方を救う!?」では、ガストロノミー・ツーリズムが紹介されていました。日本は、世界の美食家たちからは「聖地」と呼ばれるまでになっていること。地域に経済効果を生むなど、新しい日本の観光の可能性があると紹介されていました。
2013年12月4日に「和食」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。日本の伝統的な食文化として、「自然の尊重」という日本人の精神を体現した食に関する「社会習慣」を指します。世界中のガストロノミーを惹きつける日本のガストロノミー・ツーリズムがさらに進展するということは、日本の魅力がさらに増すことになります。
地域の伝統的な食文化を守ることが、世界的な評価になっていきます。地域ならではの料理も食材の産地が無くなってしまえば、そうした食習慣も廃れていってしまいます。産地をどう守っていくのか。担い手をどうのように育んでいくのか。課題は多いけれどもそうした取り組みが地域創生のカギを握っているのかもしれません。
うむっさん