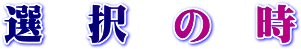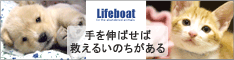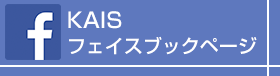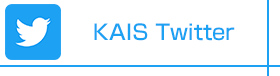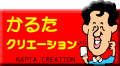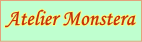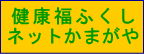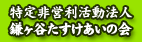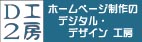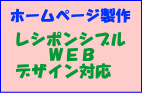-
-

選択の時
-
「心の内に分け入ってみよう」というナレーションが印象的なNHK「英雄たちの選択」。歴史に残る大きな決断をした英雄たちの「選択のとき」にせまり、その決断の意味を考えていくという番組です。英雄ではないけれど、私たちも「大なり小なり」の「選択のとき」を経た決断の結果として今の暮らしがあるわけです。
例えば、テレビ東京の人気番組「孤独のグルメ」では、主人公の井之頭五郎さんが空腹を満たすため、「何が食べたいんだ?」と店を探します。探し出したお店では、数あるメニューから「あれはどうだ。これはどうだ」と迷いに迷いながら決断していきます。しかし、ときには、隣のお客さんのオーダーをみて「やはりあれが良かったかも?」という、ちょっと悔しい思いも織り交ぜながら、食後の満足感に包まれていくというストーリーになっています。そんな「選択のとき」は、いつも私たちの身近にあります。
身近な「選択のとき」といえば、選挙が思い浮かびます。衆議院・参議院選挙、知事・市長・町長・村長の首長選挙や各議会の議員選挙があります。選択の第一段階は、「投票する」か「投票しない」です。「投票しない」の場合には、立候補者への全幅の支持と不支持が混在しているように思います。「投票する」という選択をした場合でも、「あの選択は間違った!」という場合のための仕組みも用意されています。地方自治体の選挙の場合には、「地方自治法」によって選挙権のある者に「議会の議員、長、副知事・副市長などの解職請求権」が規定されています。
つまり、選挙で「間違った選択をしたとき」にその選択を変更するための仕組みが用意されているわけです。この場合、一人ではできないのはもちろんで、有権者の1/3以上の署名が必要になります。 それぞれの選挙での「低投票率」が問題になっています。投票しなかった理由として、「選挙にあまり関心がない」「政党の政策や候補者の人物像など、違いがよくわからない」「適当な政党も候補者もいなかった」というものがあります。政治家への不信感は政治そのものに対する虚無感をも生み出していくのでしょう。その結果、投票行動という「選択のとき」そのものを避けてしまってることもあるように思います。
また、ちょっと驚いたのは「政治のことがわからない者は投票しない方がいいと思ったから」という回答が少なからず有ります。政治は「私たちの営みを支えるもの」だという立ち位置からは「えぇ!そうなんだ・・・」としか言いようがないのですが。 私たちの選択では、二者択一によって物事を決めることが選択という意識があるように思います。論語に「子曰はく、中庸の徳たる、其れ至れるかな。民鮮なきこと久し」(第6章雍也編)とあります。中庸という概念は至極難しいものですが、「中庸の徳」がなくてはならないのだとしています。
「白か黒か」「〇か×か」「右か左か」とそんなに単純に決めることができることばかりではありません。また、「空気に流された選択」では、私たちの幸せに直結しないことが間々あるように思うのです。
うむっさん